目次
私はこれまで、医療・福祉・企業・行政・教育の現場を横断しながら、女性のキャリア支援や意思決定支援に関わってきました。
その中で最も根深いと感じるのが、「教育現場におけるジェンダー平等の壁」です。
ジェンダー教育という言葉は広く知られるようになりましたが、現場ではまだ「意識」「制度」「環境」の3つの壁が存在しています。
本稿では、教育という社会の土台から見たジェンダー平等の課題と、次世代の意思決定力を育てるための戦略を考えていきます。
無意識の「ジェンダーバイアス」が学びを制限している

小学校や中学校の授業の中で、男女の役割を無意識に分けてしまう場面は今も多く見られます。
たとえば理科の実験で男子が「主導」、女子が「記録係」を担うケースや、家庭科・技術の選択科目で固定観念が働くケースなど。
これは教師の悪意ではなく、社会に染み付いた「無意識のジェンダーバイアス(性別による無意識の偏り)」の反映なのです。
その積み重ねが、「自分には向いていないかもしれない」「得意ではない」といった思い込みを生み、進路選択や職業意識にも影響していきます。
教育現場の男女比が「ロールモデルの多様性」を妨げる

教育現場そのものの構造にも偏りがあります。
たとえば小学校では女性教員が多数を占める一方で、管理職や大学教員になると男性の割合が急増します。
「先生=女性」「校長=男性」といった構図は、子どもたちの意識形成にも影響を及ぼします。
多様なロールモデルが存在しないことは、「自分もなれるかもしれない」という想像力を奪うことと同義なのです。
教科書とカリキュラムに潜む構造的な偏り
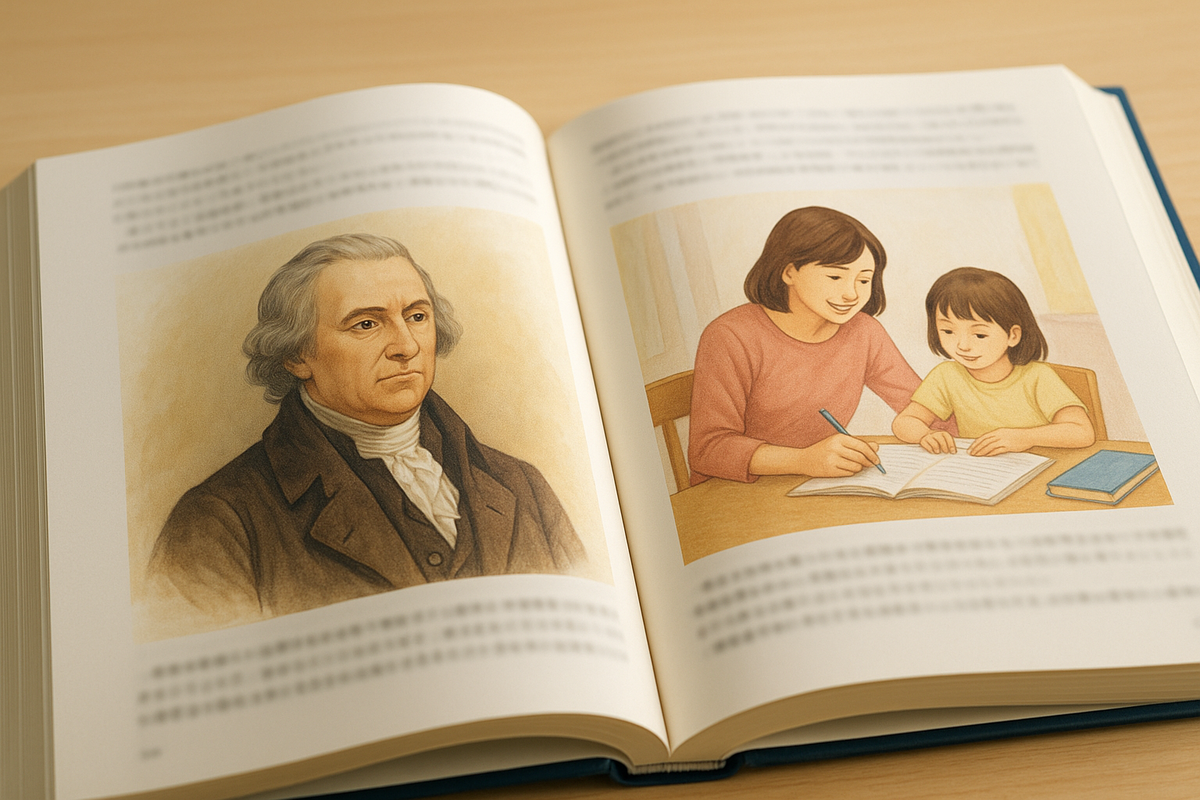
教育の内容そのものにも、性別の偏りが存在します。
たとえば教科書に登場する偉人・科学者・政治家の多くが男性であること、また家庭・育児に関する描写が女性中心で描かれること。
このような表現の蓄積が、「社会の主役は男性である」という前提を子どもたちに無意識のうちに刷り込んでしまいます。
カリキュラム設計の段階で、性別の多様性やジェンダー視点を意識的に取り入れることが求められています。
保護者・地域社会の「文化的固定観念」

教育は学校だけで完結しません。
保護者の価値観や地域社会の文化も、子どものジェンダー意識に大きな影響を与えます。
「女の子なんだから」「男の子なんだから」という言葉が、いまだに家庭や地域の中で日常的に使われている現実があります。
教育現場がいくら改革を試みても、家庭教育の価値観が変わらなければ、平等の実現は難しいのです。
「ジェンダー教育」は“特別な授業”ではない

ジェンダー教育というと、「特別な授業」や「性教育の一部」として扱われることが多いのですが、実際はそうではありません。
本来のジェンダー教育とは、「多様性を理解し、自分と他者を尊重する力」を育てる全人格教育の一部なのです。
算数でも理科でも国語でも、どの教科にもジェンダー視点は存在します。
それを日常の中でどう自然に組み込むかが、教育の質を左右する時代に入っています。
教員研修と学校組織の“ジェンダー感度”を高める

制度改革の前に、まず現場の意識改革が必要です。
教員がジェンダー視点を持たないまま教育を行うと、無意識の偏りが再生産されてしまいます。
文部科学省のガイドラインだけでなく、学校単位での研修やディスカッションを通して「気づき」を育てることが欠かせません。
また、学校運営や意思決定の場に女性教員がより多く関わることで、組織の多様性が広がります。
子どもたちが「自分で選べる社会」を育てる教育へ

最終的な目標は、男女の数を均等にすることではありません。
「どんな性別であっても、自分で選び取れる社会」を育てることです。
そのためには、子どもたち一人ひとりが“自分の意思で選択できる力”を身につける教育が必要です。
それこそが、ジェンダー平等教育の本質であり、未来の社会変革の基盤になるのです。
教育は“社会の鏡”であり、未来の設計図である

教育は社会の反映であると同時に、未来を設計する力でもあります。
つまり、教育現場のジェンダー平等を進めることは、社会全体の構造を変えることに直結しています。
制度の改革だけでなく、日常の一つひとつの言葉や態度の中にこそ、変革の芽がある。
“気づく力”と“問い続ける姿勢”を育てることが、次の世代にとって最も重要な教育なのです。

